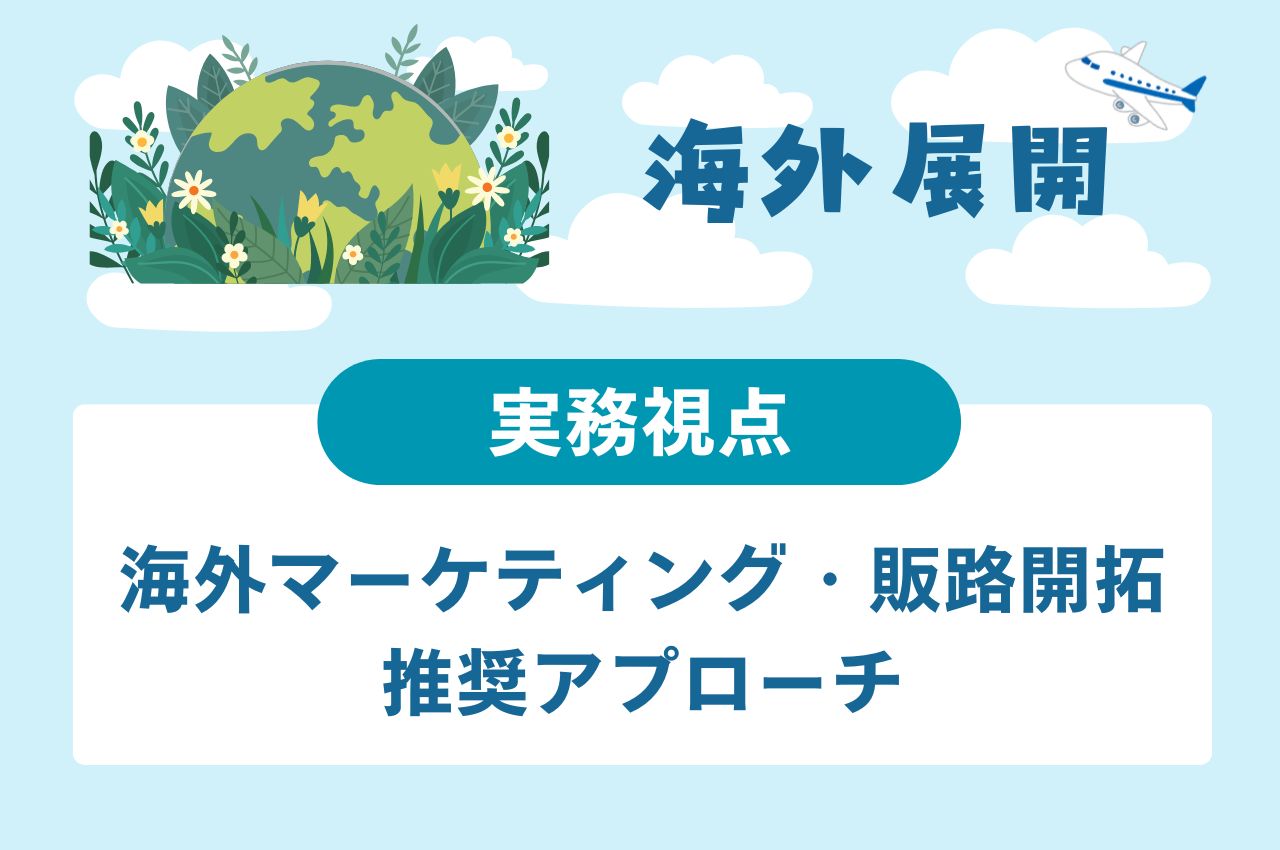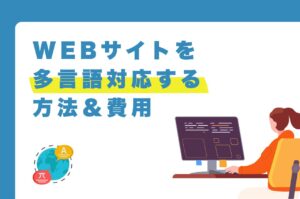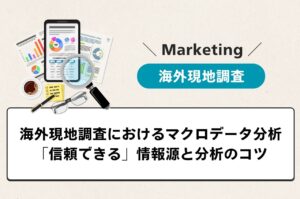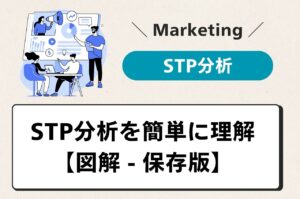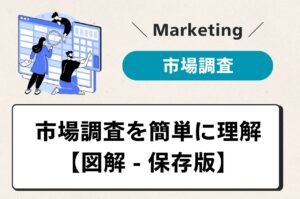初めて海外展開をご検討中の皆様へ、海外マーケティングと販路開拓における実務的なアプローチを解説します。
海外マーケティングも、基本は国内のマーケティングと考え方は同じです。そのため、一般的なマーケティングの知識に不安のある方は、まず関連記事で基本を押さえてから本記事を読み進めていただくことをお勧めします。
Step1:「対象国」×「対象製品」アプローチを理解する
海外への販路開拓で最初に行うべきは、仮説を立て、市場調査によってそれを検証することです。このプロセスを経て、現時点で最適と考えられる「対象国 × 対象製品」の組み合わせを決定します。この組み合わせを決める際には、大きく3つの考え方があります。
- マーケットイン志向
現地のニーズを的確に捉えた製品を投入するため、販売に至る可能性が高いアプローチです。ただし、市場のニーズに合う自社製品がない場合、製品改良や新規開発が必要となり、相応のコスト(人材・資金)がかかります。また、新製品は国内での販売実績がないため、商談の難易度が高くなる傾向があります。 - プロダクトアウト志向
まず戦略的に販売したい自社製品を決め、次にその製品のニーズがある国を探すアプローチです。ニーズのある国を効率的に見つけられれば、スムーズに展開できます。しかし、既存製品は海外のニーズを想定して開発されていないことが多く、そのまま販売するのは難しいケースが少なくありません。 - ローカライズ志向
まず戦略的に販売したい製品を選び、そのニーズがある国を探す、という点ではプロダクトアウト志向と同じです。しかし、その後の現地調査やバイヤーからの意見を基に、既存製品を現地向けに最適化(ローカライズ)して市場に投入する点が大きく異なります。
推奨されるアプローチ
「①コストを抑える」「②スピーディーに進める」「③成約の確度を高める」という3つの視点を踏まえると、ローカライズ志向を基本とした以下のアプローチが有効です。
- 最も自社優位性が高いと見込まれる既存製品を選ぶ。
- ニーズが高いと想定される国を絞り込み、その製品の販売可能性を調査する。
- 調査の結果、
- そのまま販売できる場合 → 販売を開始する。
- ローカライズが必要な場合 → 可能な範囲で製品を改良する。
- ニーズがない、またはローカライズが非現実的な場合 → 国または製品から再検討する。
既存製品をそのまま販売できるのが理想ですが、「ある程度のローカライズは必要になる」という前提で販路開拓に臨むのが現実的です。自社の強みである製品を現地向けに最適化して投入するこのアプローチは、成功の確度を相対的に高めながらPDCAを回せる、建設的かつ合理的な手法と言えるでしょう。
Step2:製品を絞り込む(初期仮説を立てる)
コストを抑え、効率的に現地調査を行うためには、最初の仮説段階で「海外向けの戦略製品をいかに的確に選定できるか」が重要になります。
マーケティングの基本に倣うと「ニーズ」から考えたくなりますが、特にリソースが限られる中小企業の場合、まずは「国」ではなく「製品」から検討することをお勧めします。
国からアプローチすることを推奨しない理由は、以下のケースを想像すると分かりやすいでしょう。
【Case】
製造現場向けの製品を作るA社は、今後の販売ターゲット国として「人件費が安く、税制優遇等もあるため、今後製造業者が生産拠点として注目するだろう」という理由でB国の製造業者に狙いを定め、現地調査を行いました。
その結果、自社の製品カテゴリやラインナップに一定のニーズがあることが判明しました。
しかし、その製品は自社にとって競争力の高い主力製品ではなく、あくまで品揃えを拡充するための補完的な製品であり、特に競争優位性があるものでもありませんでした。
一方、A社が競争優位性を有する製品は、別のカテゴリであり、現地では特にニーズがないことが分かりました。
このように、先に「国」から入ると、現地のニーズと自社の強みを持つ製品が一致しない可能性があり、調査が無駄に終わるリスクがあります。
実務視点における海外販路開拓では、まず日本で売れている自社製品を軸に、その製品が売れる市場(マーケット)を探すアプローチを推奨します。その上で、現地に合わせる「ローカライズ」の余地を残しておくことが成功の鍵となります。
では、具体的にどのように製品を絞り込むべきか、シンプルなアプローチをご紹介します。
基本的に、国内で売れないものが海外で売れることは稀です。「文化や商習慣が違うから、日本では売れなくても海外なら売れるはずだ」という声も聞かれますが、その多くは希望的観測に過ぎません。合理的に進める上で、実績のない製品を初期仮説に据えるのは得策ではありません。
販売数量が多い製品の中から、競合他社と比較して競争力が高いと言える製品を順位付けします。この「競争力」は、国内の顧客が製品に求める要件をリストアップし、製品ごとに評価することで判断します。そこそこ売れていても競争力に乏しい製品は、海外ではいずれ他社にシェアを奪われる可能性が高いです。
上記2まででも十分ですが、代理店などを通じて販売する場合は、「売りやすさ」も重要な要素です。例えば、メンテナンスが容易である、説明がシンプルであるといった「手離れの良さ」は、代理店にとって大きな魅力となります。国内で代理店を活用している場合は、彼らの意見をヒアリングしてみましょう。
Step3:販売国を絞り込む(初期仮説を立てる)
海外向けの戦略製品が定まったら、次はターゲットとなる国を絞り込みます。現在、世界には196の国があり(※2021年外務省発表)、すべてを調査するのは不可能です。そのため、まずはニーズがありそうな国や地域に見当をつける必要があります。
ここでは、大局的な視点(マクロ)から具体的な候補(ミクロ)へと絞り込んでいく作業を行います。
アプローチ例
まずは販売候補国をリストアップし、要件に沿って序列化するイメージで進めましょう。初期仮説の段階で詳細なマクロデータを分析しても良いですが、限られたリソースの中では、まず以下の要件で候補を絞り込み、その後に定量的なデータを比較していく方が効率的です。
- 業界動向でよく見聞きする国
新聞、業界ニュース、セミナーなどで頻繁に名前が挙がる国は、時期の差こそあれ、ニーズが期待できる候補としてリストアップしましょう。ただし、その国が「販売国」として魅力的なのか、「生産国」として魅力的なのかは大きな違いですので注意が必要です。 - 既存顧客の動向や担当者からよく聞く国
既存顧客が製品をどのように扱っているかは重要なヒントになります。例えば、顧客の海外工場で自社製品が使われている場合、その国は将来の有望な販売先候補となり得ます。 - 競合他社が輸出している国
競合他社がすでに輸出している国は、市場ニーズが存在する証拠です。企業のウェブサイトなどで輸出実績を公開している場合もあるため、確認しておくと良いでしょう。 - 過去に引き合いがあった国
当然ながら、これまでに問い合わせや引き合いがあった国は有力な候補です。どの国の、どの顧客から、どの製品に引き合いがあったのかを整理し、リストアップしておきましょう。
Step4:マクロ環境・事業環境の分析で仮説を検証する
製品と国の候補を数カ国に絞り込んだら、いよいよ現地調査のフェーズです。ここでの目的は、「その国で、この製品のニーズはあるか?」という問いに明確な結論を出し、次の戦略策定へと進むことです。
調査方法は、大きく2つに分けられます。
- 現地での実地調査
自分の目で直接現地の市場や状況を確認するのが理想です。ただし、時間やコスト、専門性を考慮し、調査会社のような専門家に依頼するのも有効な手段です。 - インターネットでの調査(デスクトップリサーチ)
旅費などのコストを抑えられるため、予算が限られている場合に有効です。
本来は、まずインターネットで事前調査を行い、その結果を持って現地で実地調査を行うのが理想的な流れです。目先のコストを惜しんで調査が中途半端になると、その後のプロセスが停滞し、結果的に数ヶ月の時間を無駄にしかねません。失われた時間を人件費に換算すれば、その損失は計り知れないでしょう。
アプローチ例:デスクトップリサーチでマクロ環境を比較する
まずは、PEST分析などのフレームワークを活用し、マクロ環境を国ごとに比較・分析してみましょう。PESTとは、Politics(政治)、Economics(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の頭文字を取ったもので、この4つの視点から国を分析することで、全体像を網羅的に捉えることができます。
PEST分析例(簡易)
- 政治(Politics)
- 事象: ベトナム政府が新たな工業化戦略を発表した。
- 仮説への影響: 販路候補としてのベトナムの優先度が上がる。
- ポイント: 新たな5ヵ年計画で、従来の機械分野に加え、自社の強みであるエコ関連分野も重点化されることが判明した。
- 経済(Economics)
- 事象: CLM諸国(カンボジア、ラオス、ミャンマー)のGDP成長率が3年連続で高い。
- 仮説への影響: 長期的な視点で販売可能性を調査する価値があると判断。
- ポイント: 主要なターゲットではないが、成長の背景を深掘りし、将来的な市場として注視し続けることにした。
- 社会(Society)
- 事象: インドネシアやフィリピンなどで、今後「人口ボーナス期」が本格化する。
- 仮説への影響: 販路候補として有望な国と判断。
- ポイント: 労働人口が増加するこれらの国々は、自社製品の特性上、長期的に好ましい市場環境であることが分かった。
- 技術(Technology)
- 事象: インドネシアとCLM諸国は、インターネット普及率が依然として低い。
- 仮説への影響: 販路候補としての優先度が下がる。
- ポイント: 自社製品の普及にはインターネット利用が不可欠なため、現時点ではこれらの国は優先すべき市場ではないと判断した。
事業環境分析での留意点
海外の規制や認証については、必ず事前に確認が必要です。実務では、輸出時、輸入時、販売時の各段階で規制をクリアしているかを確認します。認証には必須のものと任意のものがあるため、費用対効果やリスクを考慮して申請の要否を慎重に判断しましょう。
- 国際条約の例:
- ワッセナー・アレンジメント(通常兵器等の輸出管理)
- ロッテルダム条約(有害化学物質の規制)
- バーゼル条約(有害廃棄物の越境移動規制)
- ワシントン条約(野生動植物の国際取引規制)
- 日本国内の規制例(輸出時):
- 外国為替及び外国貿易法
- 関税関連三法
- 現地の規制例(安全認証など):
- 米国:UL認証
- 欧州:CEマーキング
- 中国:CCC認証
- タイ:TIS認証
海外マーケティングでお悩みではありませんか?
ここまで、海外マーケティングにおける市場調査の重要性と具体的な進め方を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。理論は理解できても、自社だけで質の高い海外市場調査を実施するには、多くの時間と専門的なノウハウ、そして現地でのネットワークが必要となるのが現実です。もし、あなたが「何から手をつければ良いか分からない」「現地のリアルな情報が手に入らない」「分析結果をどう戦略に活かせばいいか悩んでいる」といった課題をお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちティアにご相談ください。
ティアは、海外マーケティングに豊富な実績を有し、これまで数多くの日本企業の海外進出を支援してまいりました。机上の空論ではない、現場の実態に即した精度の高い市場調査から、その結果に基づいた実行可能なマーケティング戦略の立案、そして現地での施策実行まで、ワンストップでサポートいたします。