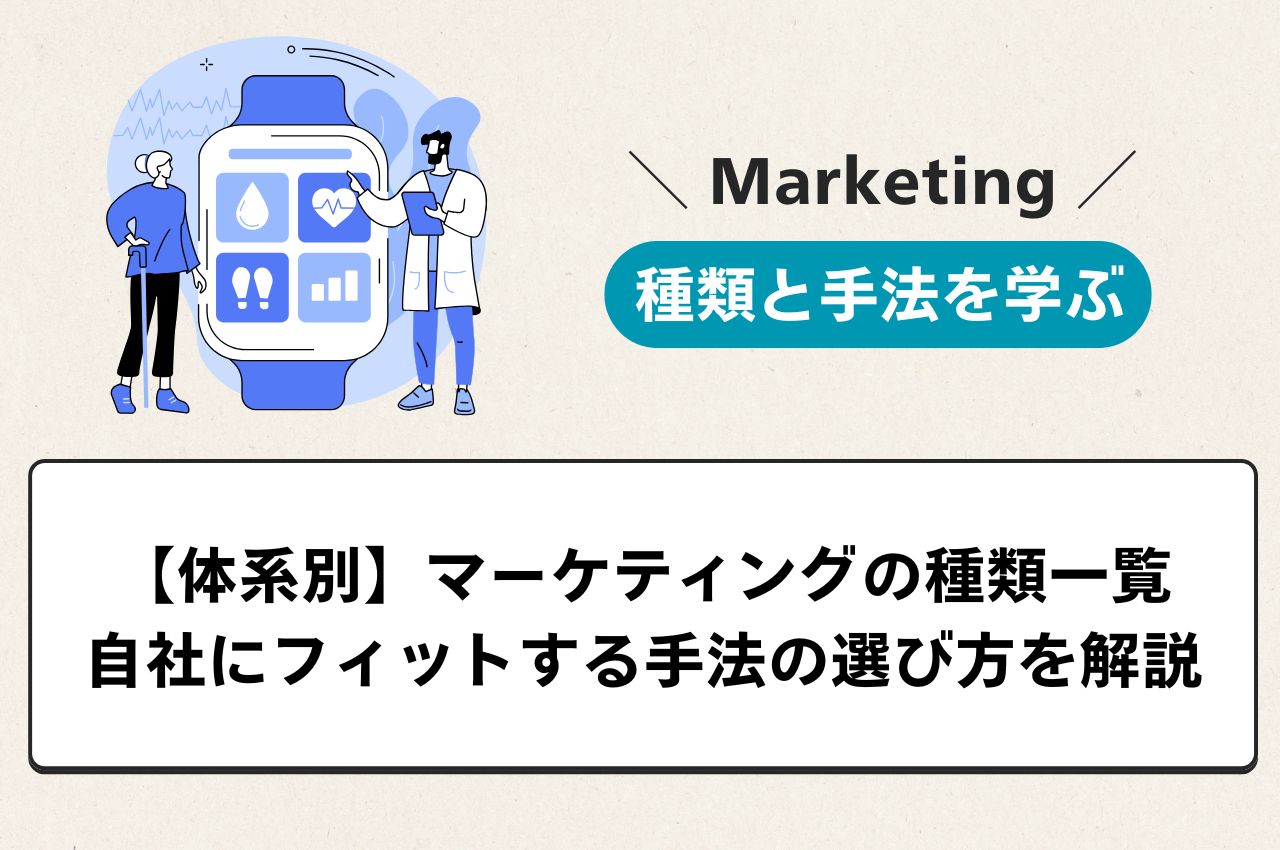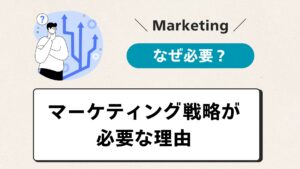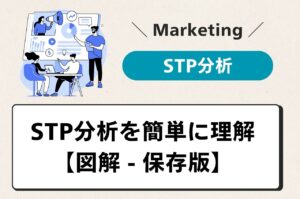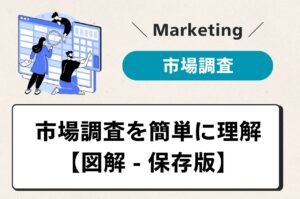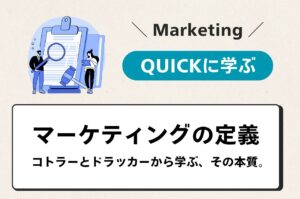「マーケティング」と一言でいっても、その手法は実に多岐に渡ります。テクノロジーの進化や消費者行動の複雑化に伴い、次々と新しいアプローチが生まれる現代において、「そもそも、どんな種類があるのだろう?」「自社には、一体どの手法が最適なのか?」といった疑問を抱える担当者様も少なくないのではないでしょうか。
人々の嗜好は多様化し、企業と顧客の接点も無数に存在する。そのような状況下でやみくもに施策を打っても、期待する成果は得られにくいのが現実です。だからこそ、各マーケティング手法の特性を体系的に理解し、自社の置かれた状況と目的に合わせて正しく選択・組み合わせる「戦略的視点」が、今ほど求められている時代はありません。
この記事では、数多くの種類の中から最低限押さえておくべき基本的な手法を体系的に整理します。単なるリストの紹介に留まらず、自社に最適な手法を見極めるための「選び方の指針」まで、我々の経験を踏まえて分かりやすく解説を進めてまいります。
なぜ今、多様なマーケティング手法を理解する必要があるのか?
先ず、本題に入る前に、なぜこれほどまでにマーケティング手法の理解が重要視されるのか、その背景を少しだけ掘り下げてみましょう。結論からいえば、それは「顧客」を理解するためです。かつてのように、画一的なメッセージを一方的に発信するだけのマスマーケティングが通用した時代は終わりを告げました。
現代の顧客は、自ら情報を検索し、SNSで他者の評価を参考にし、複数のチャネルを自由に行き来しながら購買を決定します。彼らがどこで、何を求め、どのように意思決定しているのか。その複雑なプロセスを解き明かし、適切な場所で、適切な価値を提供するためには、我々マーケター側も多様なアプローチ方法という「武器」を持っておく必要があるのです。
手法の引き出しが多ければ多いほど、顧客に対する解像度は高まり、より精度の高い戦略を描くことが可能になります。それは、無駄な広告費を削減し、営業活動を効率化し、ひいては企業の持続的な成長を実現するための、極めて重要な第一歩といえるでしょう。
マーケティングの種類を捉えるための「3つの視点」
さて、無数に存在するマーケティング手法ですが、闇雲に一つひとつを覚えても全体像は見えてきません。そこで、これらを整理し、理解を深めるために有効な「3つの視点(分類軸)」をご紹介します。この軸に沿って見ていくことで、各手法の位置づけや役割が明確になり、頭の中が整理しやすくなるはずです。
- 視点1:対象顧客で分類する
誰に対してマーケティングを行うのか、という最も基本的な分類です。 - 視点2:アプローチ手法で分類する
どのようなチャネルやメディアを使って顧客にアプローチするのか、という視点です。 - 視点3:顧客との関係性で分類する
企業と顧客、どちらから働きかけるかという方向性の違いによる分類です。
それでは、これらの視点に沿って、具体的なマーケティングの種類を順に確認していきましょう。
【視点1】対象顧客で分類するマーケティングの種類
先ず最初の切り口は、「誰に売るのか?」という視点です。相手が一般消費者なのか、あるいは法人なのかによって、意思決定のプロセスや重視されるポイントが大きく異なるため、マーケティングのアプローチも根本的に変わってきます。
BtoCマーケティング
「Business to Consumer」の略であり、企業が一般消費者に対して商品やサービスを販売する際のマーケティング活動全般を指します。街の小売店や飲食店、アパレル、家電メーカーなどがこれに該当しますね。BtoCマーケティングの特徴は、個人の感情や流行、ブランドイメージといった心理的要因が購買に大きく影響する点です。そのため、ブランディングや広告を通じた認知度向上、SNSでの共感を呼ぶコミュニケーションなどが重要になります。
BtoBマーケティング
「Business to Business」の略で、企業が他の法人に対して商品やサービスを販売する際のマーケティングです。生産財や業務システム、法人向けSaaS、コンサルティングサービスなどが分かり易い例でしょう。BtoBでは、個人の感情よりも、価格の妥当性、機能性、費用対効果といった「経済合理性」が強く求められます。また、購買決定には複数の部署や役職者が関与するため、意思決定プロセスが長く複雑になりがちです。その結果、Webサイトでの詳細な情報提供やセミナー開催、営業担当者による継続的な関係構築といったアプローチが有効となります。
BtoB2Cマーケティング
少し応用的なモデルですが、「Business to Business to Consumer」という形態も存在します。これは、企業(B1)が別の企業(B2)を介して、その先にいる一般消費者(C)にアプローチするモデルです。例えば、食品メーカーがスーパーマーケットに商品を卸し、スーパーが消費者に販売するケースや、楽天市場のようなECプラットフォーマーは典型的なBtoB2Cモデルといえます。この場合、流通チャネルとなってくれる法人(B2)への働きかけと、最終消費者(C)への働きかけ、その両面からのマーケティング戦略が必要になります。
【視点2】アプローチ手法で分類するマーケティングの種類
次に、「どのように顧客と接点を持つか?」というチャネルの視点で分類します。これは、デジタル技術の浸透によって最も多様化が進んだ領域であり、オンラインとオフラインの使い分け、あるいは融合が戦略の鍵を握ります。
オフラインマーケティング
インターネットを介さない、所謂「リアルな世界」でのマーケティング活動を指します。テレビCMや新聞・雑誌広告といった4大マスメディア広告のほか、交通広告、チラシのポスティング、展示会への出展、セミナー開催、ダイレクトメール(DM)などが挙げられます。不特定多数に広くリーチできる、あるいは特定のエリアやコミュニティに直接アプローチできる点が強みですが、効果測定が難しい、コストが比較的高くなりがちといった側面も持ち合わせています。
オンラインマーケティング(デジタルマーケティング)
WebサイトやSNS、Eメール、スマートフォンアプリといったデジタル技術を活用するマーケティングの総称です。オフラインに比べて、施策の効果をデータで詳細に分析できる点、そしてターゲットを細かく設定してアプローチできる点が最大の強みといえます。その手法は非常に多岐にわたるため、次項でさらに深掘りして解説しましょう。
【深掘り】オンラインマーケティングの主な種類
オンラインマーケティングは種類が非常に多いため、ここでは代表的なものに絞って紹介します。これらは独立しているのではなく、相互に連携させることで効果を最大化できる、という視点を持つことが重要です。
- Webマーケティング
自社のWebサイト(ホームページ)を基点としたマーケティング活動です。検索エンジンからの集客(SEO)やWeb広告の運用、サイト内での回遊率やコンバージョン率の改善(LPO/EFO)などが含まれます。全てのオンライン施策の受け皿となる、まさに中心的な存在です。 - コンテンツマーケティング
読者にとって価値のあるブログ記事やノウハウ資料、動画などの「コンテンツ」を継続的に発信することで、潜在的な顧客との接点を持ち、信頼関係を築きながら、最終的に購買へと繋げる手法です。広告のように即効性はありませんが、良質なコンテンツは資産として蓄積され、中長期的に安定した集客をもたらしてくれます。 - SEM(検索エンジンマーケティング)
GoogleやYahoo!などの検索エンジンを活用したマーケティングの総称です。これには、検索結果の上位表示を目指す「SEO(検索エンジン最適化)」と、検索結果画面に広告を出稿する「リスティング広告」の2つが含まれます。ニーズが顕在化しているユーザーに直接アプローチできる、極めて強力な手法です。 - SNSマーケティング
Facebook, Instagram, X (旧Twitter), LinkedInなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用する手法です。情報発信によるブランディングやファン育成、ユーザーとの直接的なコミュニケーション、そしてSNS広告の配信など、その活用方法は多岐に渡ります。情報の拡散力が高い点が大きな魅力といえるでしょう。 - インフルエンサーマーケティング
SNSなどで多くのフォロワーを持つ「インフルエンサー」に自社の商品やサービスを紹介してもらい、認知拡大や購買促進を狙う手法です。企業からの直接的な発信よりも、消費者目線に近い第三者の声として受け入れられやすい点が特徴です。
| インフルエンサーの種類 | フォロワー数 |
| メガ | 100万人以上 |
| ミドル | 10万人~100万人 |
| マイクロ | 1万人~10万人 |
| ライト | 1千人~1万人 |
- Eメールマーケティング
所謂「メルマガ」に代表される、Eメールを活用した古くからある手法です。獲得した見込み客リストに対して、ステップメール(予め設定したシナリオに沿って自動でメールを配信する仕組み)やセグメント配信を行うことで、顧客を育成し、関係性を深めていく目的で利用されます。MailchimpやBenchmarkといったHTMLメールサービスが有名です。
【視点3】顧客との関係性で分類するマーケティングの種類
最後の切り口は、企業と顧客のどちらがアプローチの主導権を握るか、という視点です。これは「プル型」「プッシュ型」とも言い換えられます。
インバウンドマーケティング
前述のコンテンツマーケティングに代表される、「顧客側から自社を見つけてもらう」ことを主眼に置いたマーケティング手法です。有益な情報を発信することで顧客を引きつけ(Pull)、問い合わせや資料請求といった自発的なアクションを促します。広告色が薄いため顧客に受け入れられやすく、長期的な資産構築に繋がる一方、成果が出るまでに時間を要するのが特徴です。まさに「待ち」の姿勢のマーケティングといえます。
アウトバウンドマーケティング
インバウンドとは対照的に、「企業側から顧客に対して積極的に働きかける」手法です。テレビCMやテレアポ、プッシュ型の広告、展示会での名刺交換などがこれに当たります。短期的に多くの潜在顧客にアプローチできる点がメリットですが、興味のない顧客にとっては「押し売り」と受け取られるリスクも伴います。こちらは「攻め」の姿勢のマーケティングといえるでしょう。
異分野学術視点
ニューロマーケティング
ヒトの感覚運動、潜在的な無意識含めた認知、感情的反応等、脳科学の知見を取り入れた商業コミュニケーション分野のマーケティングを指します。人間の感覚や認知、感情といった脳の働きを科学的に分析し、その知見をマーケティングに応用する分野です。
例えば、アイトラッキング技術で顧客の視線の動きを追跡し、広告デザインを最適化する。あるいは、脳波を測定して商品パッケージに対する無意識の感情的反応を探る。このように、顧客自身も言葉にできないような潜在的な反応を捉え、商業コミュニケーションに活かしていく、極めて専門的なアプローチといえます。
行動経済学
厳密には学問として成立しており既にノーベル賞受賞者が複数いる学問ですが、マーケティングの第一人者ともいえるフィリップコトラーが「行動経済学はマーケティングである」と述べたことは有名です。従来の経済学はヒトは合理的な意思決定をするという前提に立っていますが、行動経済学では、それに異を唱えた学問であり、経済学に加えて人間の心理学を重要視している点が従来の経済学との違いです。
有名な論理としては価格のアンカリング等のヒューリスティックや不確実な状況下においてどのようにヒトは選択をするのか、また、工夫により自発的に意図した行動を促すナッジ理論等があります。書籍では「予想通り不合理」という本がベストセラーになりましたが、マーケティングにおいては、人間の行動経済学ベースでの意思決定を踏まえたマーケティングといえます。
自社に最適なマーケティング手法を選ぶための3ステップ
さて、ここまで様々なマーケティングの種類を見てきましたが、「では、結局どれを選べば良いのか?」という疑問が残るかと思います。最適な手法は、企業の業種や規模、ターゲット、そして目的によって全く異なります。ここでは、自社に合った手法を論理的に見つけ出すための、基本的な思考プロセスを3つのステップでご紹介します。
ステップ1:目的(KGI/KPI)を明確にする
先ず何よりも重要なのは、「マーケティング活動を通じて、最終的に何を達成したいのか」という目的を明確にすることです。例えば、「ブランドの認知度を30%向上させる」「Webサイトからの問い合わせ件数を月間50件獲得する」「新規顧客の獲得単価を2万円以下に抑える」といったように、具体的な数値目標(KGI/KPI)に落とし込みましょう。目的が曖昧なままでは、手法の良し悪しを判断する基準そのものが存在しないことになってしまいます。
ステップ2:ターゲット顧客と市場を理解する (3C/STP)
次に、自社の置かれた状況を客観的に分析します。ここで役立つのが、3C分析(顧客・競合・自社)やSTP分析(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)といったフレームワークです。
- 顧客 (Customer)
ターゲット顧客は誰で、どのような課題やニーズを持っているか?彼らは普段、どのようなメディアに接触しているか? - 競合 (Competitor)
競合他社はどのようなマーケティング活動を行っており、どのような強みを持っているか? - 自社 (Company)
自社の強みは何か?競合にはない独自の価値(バリュープロポジション)は何か?
これらの分析を通じて、「誰に」「何を」「どのように」伝えるべきかという戦略の骨子を固めます。例えば、ターゲットが高齢者層であればオフラインの施策が中心になるかもしれませんし、ニッチなBtoB商材であれば専門メディアでのコンテンツマーケティングが有効、といった仮説が見えてくるはずです。
ステップ3:手法を組み合わせ、一貫した戦略を立てる
目的と戦略の骨子が固まったら、いよいよ具体的な手法の選択に入ります。ここで重要なのは、単一の手法に固執するのではなく、顧客の購買プロセス(カスタマージャーニー)に合わせて複数の手法を組み合わせることです。
例えば、「SNS広告で潜在層に広く認知させ(認知)、有益なコンテンツで興味を引き(興味・関心)、SEOで検索してきたユーザーをWebサイトに誘導し(比較・検討)、最終的に問い合わせフォームで刈り取る(購買)」といったように、各手法が連動した一貫性のあるシナリオを描くことが、成果を最大化する上で不可欠といえます。
まとめ:マーケティング手法は「目的達成の手段」である
今回は、マーケティングの多様な種類を3つの視点から整理し、自社に合った手法を選ぶためのアプローチについて解説しました。オンラインからオフラインまで、実に多くの選択肢が存在しますが、忘れてはならないのは、これらは全て「目的を達成するための手段に過ぎない」という事実です。
流行っているからという理由だけで新しい手法に飛びついたり、過去の成功体験に固執したりするのではなく、常に「目的は何か?」「ターゲットは誰か?」という原点に立ち返ることが重要です。その上で、自社の強みを活かせる最適な手法を組み合わせ、仮説検証を繰り返していく。この地道なプロセスこそが、マーケティング戦略を成功に導く唯一の道といっても過言ではないでしょう。
この記事が、皆様のマーケティング活動における羅針盤として、少しでもお役に立てれば幸いです。
ティアのマーケティング戦略支援サービスのご案内
ここまでマーケティングの種類と選び方について解説してきましたが、「自社だけで戦略を立てるのは難しい」「専門家の客観的な視点が欲しい」と感じることもあるかもしれません。そのような課題をお持ちでしたら、ぜひ一度ティアにご相談ください。
ティアでは、これまで数多くの法人様のマーケティング課題と向き合ってまいりました。その経験と専門知識を基に、お客様の事業フェーズや目的に合わせた最適なマーケティング戦略の立案から実行まで、一気通貫でサポートいたします。複雑なマーケティングの世界で、お客様が確かな一歩を踏み出すためのパートナーとして、我々ティアが伴走します。