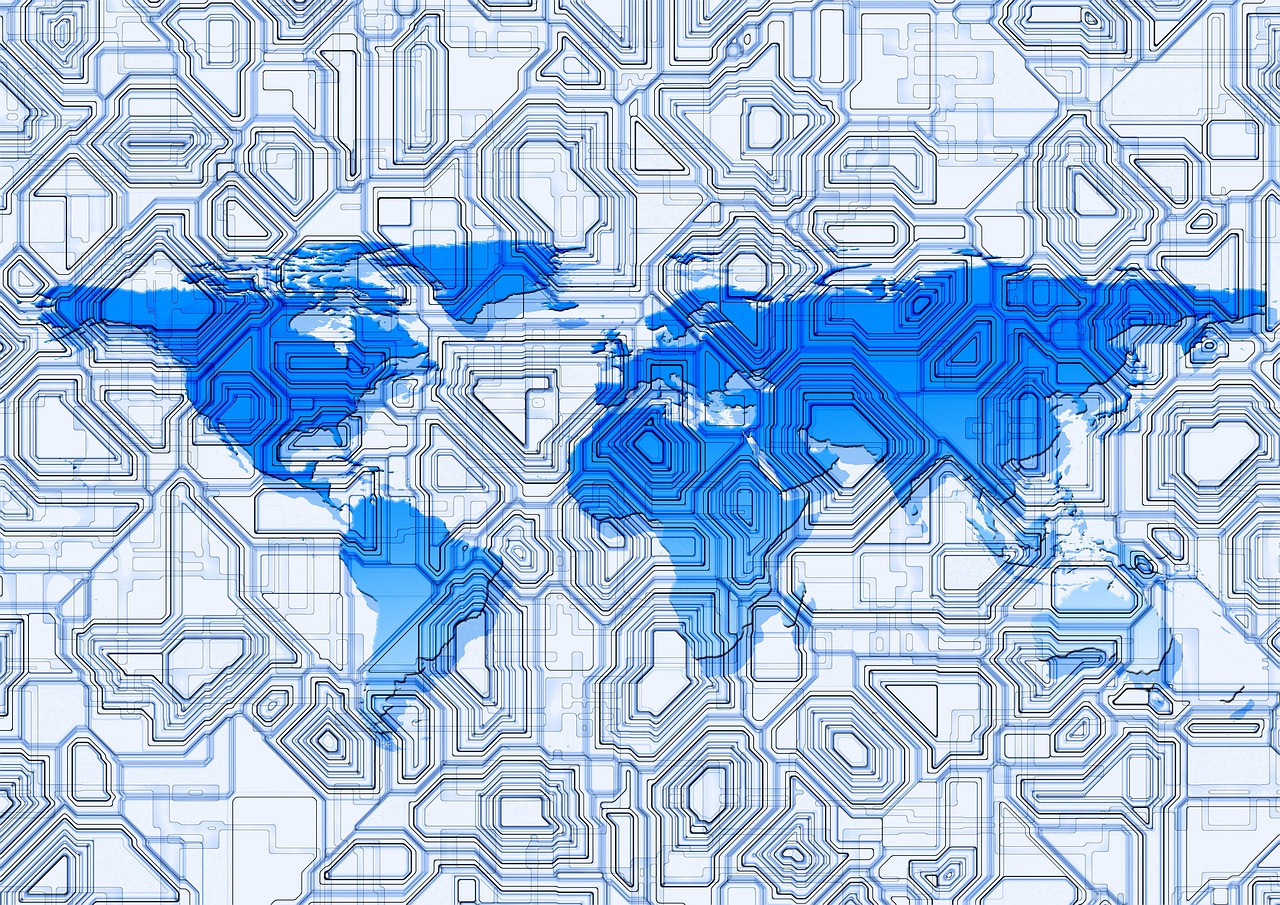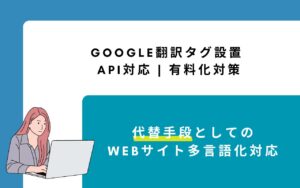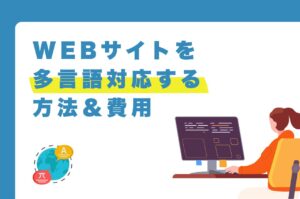海外向けのコーポレートサイトや越境ECサイトを運営する上で、多くの日本企業が「見えない壁」に突き当たります。それは、ウェブサイトの「アクセススピード」です。デザインやコンテンツにどれだけ心血を注いでも、サイトの表示が遅いというだけで、顧客はその価値に触れる前にページを閉じてしまいます。これは単なる利便性の問題ではなく、ビジネスにおける深刻な機会損失に他なりません。
この記事では、海外展開におけるこの根深い課題を解決するため、その根幹である「サーバー」の選び方に焦点を当てます。なぜ海外からのアクセスは遅くなるのか、その技術的背景から、具体的な解決策としての各種サーバー・サービスの徹底比較、そしてWordPress本家が推奨するサーバーの真実まで。小手先のテクニックではない、海外WEB戦略のまさに土台となるインフラ設計の本質を、我々ティアが培ってきた知見に基づき、余すところなく解説いたします。
WordPress海外サイトのサーバー選び完全ガイド|高速化を実現する推奨サービスと注意点を徹底解説
海外向けのコーポレートサイトや越境ECサイトを運営する上で、多くの日本企業が「見えない壁」に突き当たります。それは、ウェブサイトの「アクセススピード」です。デザインやコンテンツにどれだけ心血を注いでも、サイトの表示が遅いというだけで、顧客はその価値に触れる前にページを閉じてしまいます。これは単なる利便性の問題ではなく、ビジネスにおける深刻な機会損失に他なりません。
この記事では、海外展開におけるこの根深い課題を解決するため、その根幹である「サーバー」の選び方に焦点を当てます。なぜ海外からのアクセスは遅くなるのか、その技術的背景から、具体的な解決策としての各種サーバー・サービスの徹底比較、そしてWordPress本家が推奨するサーバーの真実まで。小手先のテクニックではない、海外WEB戦略のまさに土台となるインフラ設計の本質を、我々ティアが培ってきた知見に基づき、余すところなく解説いたします。
なぜ海外向けサイトの表示は遅くなるのか?- 無視できない物理的距離の壁
先ず、海外のユーザーが日本のサーバーに置かれたウェブサイトにアクセスする際、なぜ表示速度が著しく低下するのか、そのメカニズムを正しく理解しておく必要があります。結論から言えば、これはデータの通信における「物理的な距離」が根本的な原因です。
ユーザーがブラウザでURLをクリックした瞬間、そのリクエストは光の速さに近いスピードで、海底ケーブルなどを経由して日本のサーバーへと向かいます。そしてサーバーがそのリクエストに応じてウェブサイトのデータを送り返す。この一連のデータの往復旅行において、距離が長ければ長いほど、応答にかかる時間、いわゆる「レイテンシー(遅延)」が増大します。たとえ光の速さであっても、東京からニューヨークまで往復すれば、それだけでコンマ数秒の遅延は避けられません。
更に、距離が長くなることで、通信途中でデータの一部が失われる「パケットロス」のリスクも高まります。データが欠ければ再送要求が発生し、遅延は更に深刻化します。その結果、ユーザーの画面には真っ白なページが表示されたまま、数秒、あるいは十数秒が経過してしまうのです。Googleがサイト評価の重要指標として掲げる「Core Web Vitals」においても、表示速度はユーザー体験の根幹をなす要素とされており、SEOの観点からも決して無視できない経営課題といえるでしょう。
ここではデータに基づいてもう少し具体的に弊害となる事象を見ていきましょう。
サイト表示が2~6秒かかると4人に1人が離脱する
以前に米国企業のGomez社(現在はdynatrace社に買収されている認識)が独自調査を実施し、ページのレスポンス時間が2-4秒かかると8%のユーザーが離脱し、2-6秒の間では25%、2-8秒で33%、2-10秒で48%のユーザーが離脱すると発表しました。サーバーやアクセス速度改善の様々なツールが世の中に普及されるにつれて、検索する我々ネットユーザーも早いことが日々無意識のうちに当たり前のようになってきています。そう考えると、皆さんもご自身で検索しているときに、アクセスしたサイトが5秒も10秒もかかればサイトを閉じないでしょうか。ローディング時間が長いとそもそも途中でブラウザがエラーになることもあるので、どれだけ優れた製品やサービスを持っていても、相手にその良さが伝わる以前に商談機会を逃すことになります。完全なる機会損失であり、是が非でも避けたいところですね。
1秒サイト表示が遅れることでページビューが1割減り、CSは2割下がる
同じ調査で更に浮き彫りになったこととして、たった1秒ページがブラウザに表示されるのが遅れるだけで、ページの閲覧数が11%も減り、また目的であるコンバージョンも7%減り、顧客満足度は16%減少すると明かしています。その結果、一人当たりのレベニューも下がることになり、収入にも悪影響を与えます。ウェブサイトにおいて1秒の遅れという代償がここまで大きいとは考えものであり、アクセススピードの対策は必須であることも頷けます。
海外向け会社サイトや越境ECサイトは、地理的要因から現地競合よりも大きく不利
では海外向け会社サイトや越境ECのサイトの観点からアクセススピードを考えるとどうなるでしょう。基本的に国内の中小・中堅メーカーさんが海外向けサイトや越境ECサイトを構築する際には日本にある既存の契約しているサーバーでサイトを構築するケースが多いです。現在の日本語のサイトを多言語化する場合や新しく新規ドメインまたはサブドメインを使用して構築する場合もありますが、いずれにしても大半は国内のサーバーがサイト構築のインフラにあります。
そう考えた場合に、例えば米国を主なターゲット市場として、米国に製品もコンテンツも寄せた(=ローカライズ)させてサイトを構築したとします。
しかしながら、米国在住のアメリカ人が自社のサイトにアクセスする場合に日本のサーバーにアクセスするケースが原始的なカタチとなります。そうした場合にユーザーにとってはどのようなことが減少として彼らの身に降りかかってくるのでしょうか。もうお分かりだと思いますが、サイトの表示が米国現地の競合サイトと比べて大幅に遅れることです。
その結果、どうなるでしょう。最悪なケースは、CMS等を使用して特に何も対策を講じていなかったためサイト自体も重く、表示されずにブラウザがエラーを返した。商談機会は完全に断たれました。あるいは、5秒、10経過しても表示されずに、ユーザーがしびれを切らし、サイトを閉じた。同様に再訪は二度とないでしょう。少しマシなケースでは、ユーザーの忍耐力が勝り、サイトが開いたものの、サイト内で製品・サービスのページやAbout usのページへと遷移する中で毎回5秒、10秒と待たされ、いい加減我慢できなくなりサイトを閉じる、あるあるですね。仮にうまく設定したコンバージョンに至ったとしても、顧客満足度という観点ではいかがでしょうか。言わずもがなだと思います。きちんと対応をしていきましょう。
海外サイト高速化を実現する3つのインフラ選択肢
さて、この物理的な距離という抗いがたい制約を乗り越えるため、我々にはどのような選択肢があるのでしょうか。大きく分けて、「現地レンタルサーバー」「クラウドサーバー」「CDN」の3つのアプローチが考えられます。それぞれに一長一短があり、自社の状況に合わせて最適なものを見極めることが肝要です。順に解説していきましょう。
選択肢1:現地レンタルサーバー
最も直感的で手軽な解決策が、ターゲットとする国に物理的に存在するレンタルサーバーを契約することです。例えば、米国市場を狙うのであれば、米国内にデータセンターを持つレンタルサーバーを利用します。その結果、米国のユーザーは国内のサーバーにアクセスすることになるため、前述した物理的な距離による遅延を根本的に解消できます。
- メリット
国内のレンタルサーバーを契約する感覚と大差なく、比較的安価で手軽に導入できる点が最大の魅力です。サーバー管理の専門知識がなくても、直感的なコントロールパネルで運用可能なサービスが殆どです。 - デメリット
サポートや契約手続きが英語などの外国語になる点が一つ目のハードルです。また、ターゲット国が複数にまたがる場合、国ごとにサーバーを契約・管理する必要があり、運用が煩雑化します。 - どのような企業に向いているか?
ターゲット市場が単一の国に明確に定まっており、かつ迅速かつ低コストでインフラを整備したいスタートアップや中小企業にとって、有効な選択肢といえるでしょう。
選択肢2:クラウドサーバー(AWS, Google Cloudなど)
昨今、AWS(Amazon Web Services)やGoogle Cloudといったクラウドサーバーの存在感が増しています。これらは世界中の様々な都市(リージョン)にデータセンター網を持っており、管理画面から希望する国の仮想サーバーをすぐに立ち上げることが可能です。
- メリット
世界中のリージョンを柔軟に選択できるため、多言語・多国展開に非常に強いのが特徴です。アクセス集中に応じてサーバーの性能を即座に増強できるスケーラビリティも、ビジネスの成長に合わせて対応できる大きな利点です。 - デメリット
レンタルサーバーに比べて設定の自由度が高い反面、利用には高度な専門知識が求められます。また、料金体系が従量課金制であることが多く、コスト管理が複雑になりがちで、知識なく利用すると想定外の高額請求に繋がるリスクも孕んでいます。 - どのような企業に向いているか?
複数の国や地域へ展開を計画しており、ビジネスの成長予測が不確実な場合や、急なアクセス増が見込まれるサービスを展開する企業。また、インフラ管理を専門に行える技術者が社内にいる、あるいは外部パートナーを確保できることが前提となります。
選択肢3:CDN(コンテンツ・デリバリー・ネットワーク)
そして三つ目が、現代のグローバルサイト運営において極めて重要な役割を果たすCDNです。CDNとは、オリジナルのサーバー(例えば日本にあるサーバー)のコンテンツのコピーを、世界中に分散配置された「キャッシュサーバー」に保存しておく仕組みです。
海外ユーザーからアクセスがあった際、日本にあるオリジナルサーバーまでデータを取りに行くのではなく、そのユーザーから最も地理的に近いキャッシュサーバーが応答します。その結果、物理的な距離が劇的に短縮され、表示速度が飛躍的に向上するのです。
- メリット
現在の日本のサーバー構成を大きく変更することなく、後付けで導入できる手軽さが魅力です。世界中からのアクセスを分散して処理するため、サーバー本体の負荷軽減やセキュリティ向上にも繋がります。 - デメリット
高品質なサービスは相応のコストがかかります。また、キャッシュの仕組みを正しく理解し設定しないと、コンテンツを更新したのに古い情報が表示され続けるといったトラブルの原因にもなり得ます。 - どのような企業に向いているか?
現在のサーバー環境を維持しつつ、世界中のユーザーに対して快適なアクセス速度を提供したい、ほぼ全ての海外向けサイト運営者にとって検討すべき選択肢です。特にECサイトなど、画像の多いサイトではその効果は絶大です。
海外向けサーバー選び・実践チェックリスト
さて、これまで様々な選択肢を提示してきましたが、最終的に自社にとっての最適解を見つけるために、以下の項目を自問自答してみてください。思考が整理され、取るべき方向性が見えてくるはずです。
- 事業戦略の視点
主要なターゲット国はどこか?将来的に展開国を増やす計画はあるか? - サイト規模の視点
想定される月間アクセス数はどれくらいか?ECサイトなど動的なコンテンツや画像は多いか? - 予算の視点
インフラにかけられる初期費用と月額費用はどれくらいか?コストの優先順位は高いか? - 技術力の視点
社内にサーバー管理や英語での技術サポートに対応できる人材はいるか? - 運用の視点
サーバーの安定稼働とセキュリティ対策、どちらをより重視するか?
アクセススピードの改善は様々だが、現地サーバー起用は手っ取り早い
上記の通り、アクセススピードの改善方法は、インフラであったり、サイトのコーディングの最適化や読み込みの位置であったり、画像の最適化、安直にやると痛い思いをするキャッシュの活用であったりと様々です。しかしながらターゲット国が決まっているのであれば、その国の現地のサーバーを契約することも一案です。
なお、現地のサーバーを契約してなくてもCDNのようなサービスを使用すあればユーザーからすれば同じ状況に持ってくることもできます。ただし、それにはコストを限りなくかけないで行う方法もありますが専門的な知識が必要であったり、えてしてサービスは安くありません。そのため、今回は現地サーバーに関して簡単に触れたうえでおすすめをご紹介して締めくくりたいと思います。
現地サーバーを借りるならレンタルサーバーで十分
昨今では国内外限らずAWSがよく話題に上ります。一時的なトラフィック増加を吸収できること、従量課金制であること、またリージョンのカバレッジもAMAZONゆえに文句なしです。しかしながらAWSを理解する時間とコストを考えると国内レンタルサーバーを契約するのと同じ感覚で契約できる現地レンタルサーバーがお勧めです。またそもそも一時的なトラフィック増を吸収できることの恩恵は基本的に大手や気鋭のベンチャーでトラフィックをガンガンに得る企業になりますので、中小・中堅メーカー様の場合、特にBtoB企業様に関してはレンタルサーバーで十分といえます。
WordPress本家が推奨する海外レンタルサーバー
海外のレンタルサーバーも国内以上に五万とあります。その中でもCMSの代表格であるワードプレスと相性が良い点で昨今米国でよく取り上げられているサーバーが会社は、SiteGround、InMotion, A2 Hosting, DreamHost、WP Engine、そしてBluehostあたりでしょう。最後のBluehostですが、私たちも国内外のレンタルサーバーを4つ使用しておりますが、Bluehostもその一つだからです。
また、Bluehost自体が本家のワードプレスが推奨するサーバーでもあり、老舗的なサーバー会社です。カスタマーサポート含めたユーザーエクスペリエンスが他と比べるとちょっとね・・・という意見も欧米ではあるようですが、私はそう思いません。このカスタマサポートを購買決定要因として挙げてくるのは日本とは異なる欧米っぽさですが、サーバーやウェブサービスはやたらこのカスタマーサポートを尋常でないくらいに重視するのは面白いなぁと思います。なので日本人からするとあまり気にならないが殆どのケースではないでしょうか。
乱暴に言ってしまえば国内のさくらサーバーに近いかなと思います。さくらサーバーも使用していますが、個人的には老舗だけどカスタマーサポートはよくないと思います。ご興味のある方は是非調べてみてください。海外販路開拓の現地調査では、デスクトップリサーチでも英語検索をバンバンやる必要があるので、ひとつの練習だと思ってやってみると良いと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。海外向けサイトのサーバーを選定するということは、単にWEBサイトを置く場所を決める作業ではありません。それは、海外の顧客にビジネスの価値を届けるための、まさに土台を築く戦略的な意思決定です。この土台が揺らいでいては、その上にどれだけ美しいデザインの家を建て、素晴らしい家具を置いたとしても、いずれその価値は損なわれてしまいます。
現地レンタルサーバーの手軽さ、クラウドの柔軟性、CDNの効率性。それぞれの特性を深く理解し、自社の事業戦略と照らし合わせることで、初めて最適解は見えてきます。この地味ながらも極めて重要なインフラ選定にこそ、海外ビジネスの成否を分ける鍵が隠されているのです。先ずは手軽なレンタルサーバーから始めてみてはいかがでしょうか。
海外WEBマーケティング・サイト制作ならティア
ティアでは、海外展開を目指す企業様に対し、今回解説したサーバー選定のようなインフラ設計から、多言語サイトの構築、その後の海外WEBマーケティングまで、一気通貫での伴走支援を行っております。
「自社の場合、どのサーバーが最適なのか判断できない」「海外の技術的なやり取りに不安がある」といった課題をお持ちの企業様は、ぜひ一度当社にご相談ください。数々のグローバルサイトを成功に導いてきた実績と経験から、貴社のビジネスに最適な土台作りからお手伝いさせていただきます。